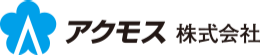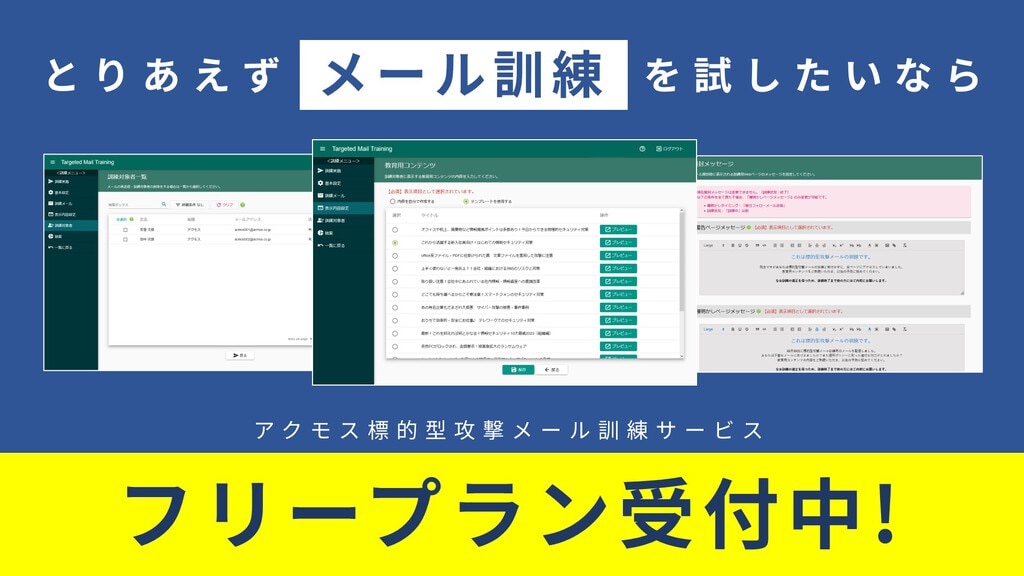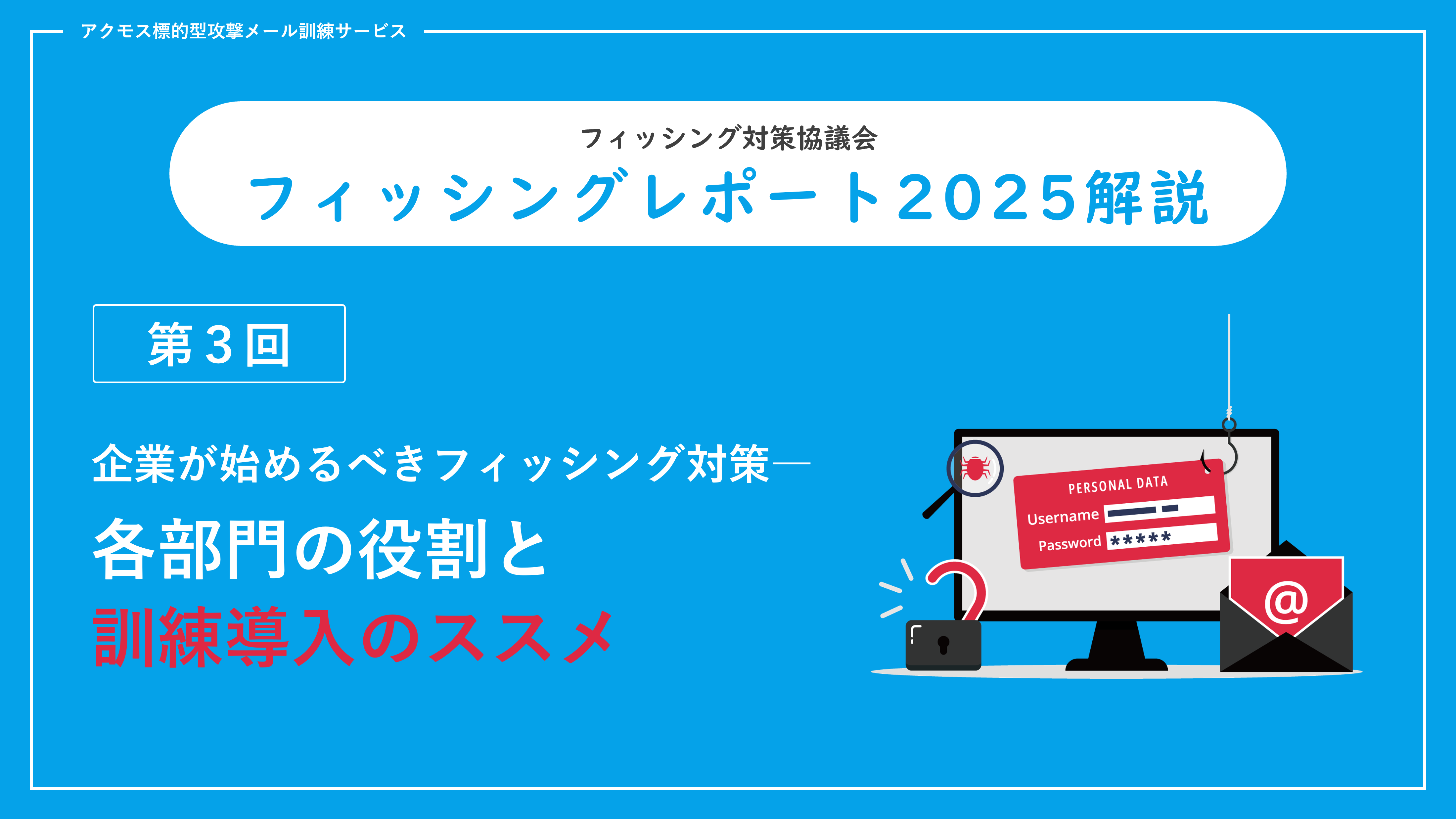
企業が始めるべきフィッシング対策―各部門の役割と訓練導入のススメ【フィッシングレポート2025・第3回】
アクモスセキュリティチームです!
最近のフィッシング詐欺は、単に「怪しいメールに注意しよう」というだけでは防げないほど、巧妙かつ多様化しています。前回の記事では、最新の手口をご紹介しましたが、今回はその“次の一手”として、企業が取り組むべき対策や訓練についてお伝えします。
「うちはIT部門に任せているから大丈夫」……そんな風に思っていませんか? 実は、全社的に取り組むことがこれまで以上に大切になっているのです。
このシリーズでは、3回に分けて企業がいま直面している脅威と、その対策についてわかりやすく解説します。
第1回目の記事:前年比1.44倍 !過去最多のフィッシング報告数から見える“サイバー脅威”とは?
第2回目の記事:被害が出る前に─進化するフィッシング詐欺の最新手口と見分けるコツ
※全3回予定/第3回目
目次[非表示]
- 1.各部門が連携して取り組むべき3つの柱
- 1.1.情報システム部門の役割
- 1.2.総務・教育部門の役割
- 1.3.経営企画・経営層の役割
- 2.「教育」だけじゃ足りない? なぜ「訓練」が必要なのか
- 3.今、企業が導入すべき「標的型攻撃メール訓練」
- 3.1.訓練をする意味とは?
- 3.2.訓練サービスのこんなポイントに注目!
- 4.まとめ
各部門が連携して取り組むべき3つの柱
情報システム部門の役割
情報システム部門は、企業の「技術的な防御線」を支える中核です。近年のフィッシング攻撃は、単に迷惑メールフィルターをすり抜けるだけでなく、正規ドメインに極めて似た偽ドメインや、ランダムに生成されたサブドメインなどを利用して、受信者を騙す高度な手法が目立ちます。
このような攻撃に対応するには、以下のような対策が必要です。
SPF/DKIM/DMARC*1の3要素を組み合わせたメール送信元認証の整備
これらはなりすましメール(ドメインスプーフィング)を技術的にブロックする鍵です。
DNSベースのブラックリスト、プロキシ経由でのURLアクセス制限などを組み合わせた防御
詐欺URLやマルウェアサイトへのアクセスをネットワークレベルで防ぎます。
「FIDO2*2/パスキー」など、ID・パスワードに依存しないフィッシング耐性のある認証手段への移行
パスキーの導入は、パスワード型認証が抱える「入力させること自体がリスク」という構造問題を根本的に解決する方向として注目されています。
脅威インテリジェンス(Threat Intelligence)の活用
最新の攻撃トレンドや詐欺URLの情報を取り入れて、常に防御のアップデートを図ります。
*1 SPF:送信されたメールのドメインが正しく、その送信元が偽装されていないかを確認する仕組み / DKIM:メール送信時に送信者が電子署名を付与し、受信者側でその署名を検証することで、送信元のなりすましやメール本文の改ざんを見抜く仕組み / DMARC:送信ドメイン認証を行うための仕組みのひとつで、SPFやDKIMの結果を活用してメールの正当性を判定する技術
*2 FIDO2:パスワードを使わずに本人確認を行える「パスワードレス認証」を可能にするためのオープンな標準仕様
総務・教育部門の役割
攻撃者は「従業員の判断力の隙」を狙ってきます。だからこそ、情報セキュリティ教育のアップデートと啓発が求められています。フィッシングレポート2025でも、以下の取り組みが効果的とされています。
定期的な社内啓発(メール、ポスター、イントラネット掲示など)
特にクイッシング(QRコード型)やスミッシング(SMS型)は、従来の「メールフィッシング」とは異なる入口を持つため、多様な注意喚起が必要です。
リアルな被害例や攻撃手法を教材化したセキュリティ研修の実施
特に、「焦らせる文面」「偽サイト誘導」「本物そっくりなログイン画面」などの実例を交えた内容が推奨されます。
従業員向け「フィッシング対策マニュアル」「注意チェックリスト」配布
普段から身につける「確認習慣」をサポートするツールとして有効です。
新入社員・中途採用者に対する研修や訓練の実施
入社時の教育タイミングを活用し、セキュリティリテラシーを標準化します。
経営企画・経営層の役割
経営層は、経営判断としてのセキュリティ対策方針を決め、組織文化としてのセキュリティ意識醸成を担う立場にあります。
セキュリティ投資の「可視化」と「継続的な評価」
費用対効果の観点での評価指標(例:訓練後のクリック率の低下、教育実施率など)を持ち、単発の対応に終わらないようにします。
CSIRT*3やSOC*4の社内整備・連携体制の構築
インシデント発生時の初動を明確にし、企業の信用失墜を最小限にとどめます。
外部の教育ベンダーとの連携や訓練導入の意思決定
標的型攻撃メール訓練のような外部リソースの活用も、効果的な手段の一つです。
トップメッセージによる全社発信
セキュリティは「現場だけの問題ではない」という意識を社内に浸透させるために、トップからのメッセージは非常に強い効果を持ちます。
*3 CSIRT:コンピュータセキュリティに関するインシデント(事故や攻撃)の報告を受け、調査や対応を担う組織のこと
*4 SOC:企業などの情報システムを対象に、脅威の監視や分析を行うための役割、または専門的な組織を指す
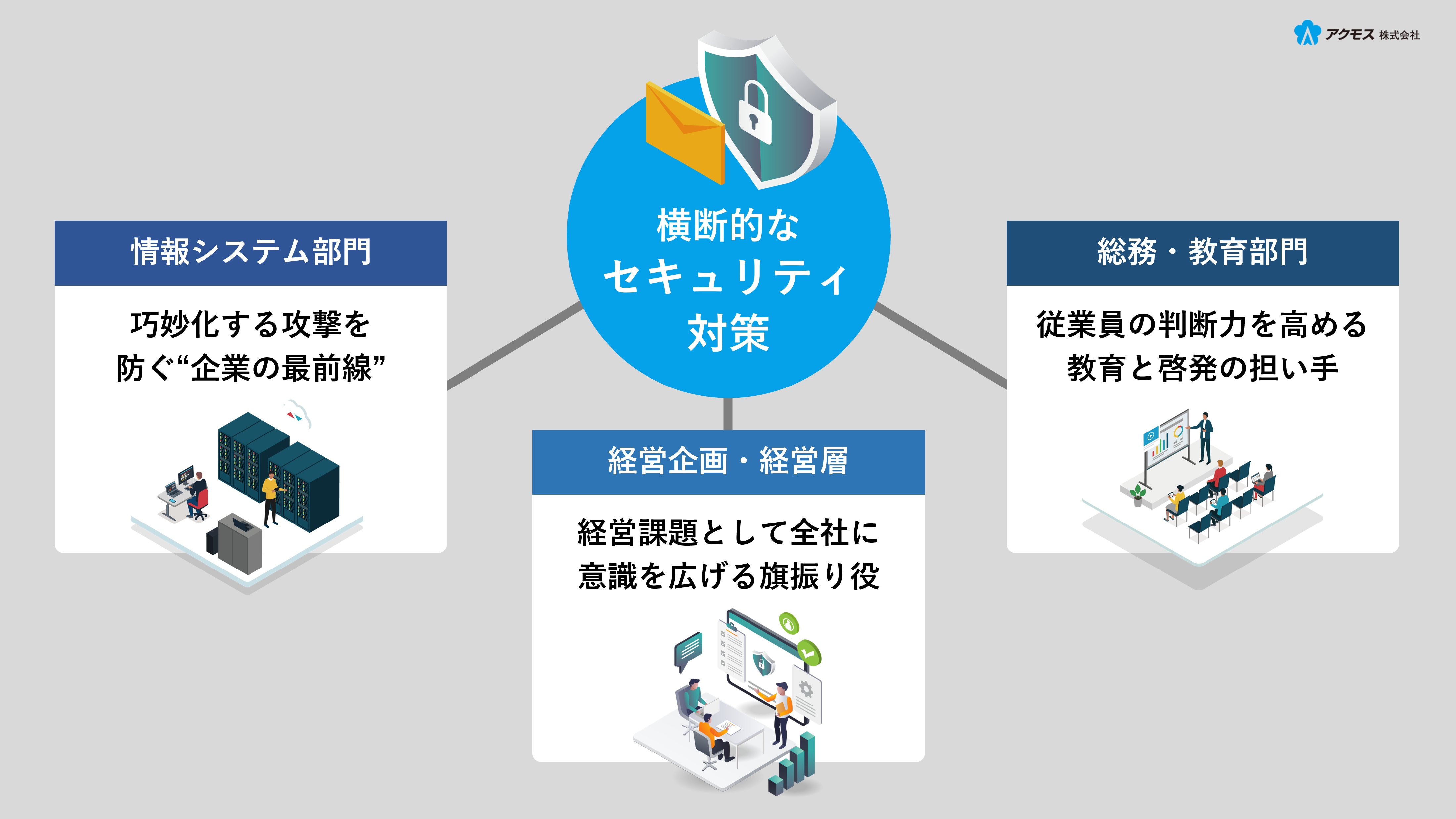
「教育」だけじゃ足りない? なぜ「訓練」が必要なのか
「注意してね」「こういうのが危ないよ」――もちろん大切な教育です。
でも、それだけでは足りないのが今の時代。
最近の詐欺メールは、ロゴや言葉遣いが本物そっくり。しかも、AIによって自然な文章が自動生成されていたりします。見た目では判断できず、違和感がまったくないのが特徴です。
だからこそ、知識を“体験”に変えるために、「訓練」が効果的。
- 実際に怪しいメールが届いたとき、どう反応するか?
- リンクをクリックしたり、情報を入力してしまう危険性に気づけるか?
この“気づき”を得るためには、実際に模擬メールを使った訓練が一番です。
今、企業が導入すべき「標的型攻撃メール訓練」
訓練をする意味とは?
- クリック率や入力率など、社員の反応を数値で見える化
- 「これって怪しいかも」と気づく力を実践で育てる
- 訓練後の振り返り資料や解説で、知識をしっかり定着させる
- 最新事例・手口を体験させる
何より、「自分は引っかからない」と思っていた人ほど、訓練で「うっかりクリックしてしまった…」ということも多いのです。
訓練サービスのこんなポイントに注目!
- 実際の詐欺メールとそっくりな内容で訓練できる
- 「宅配通知」「自治体の案内」「銀行からの確認メール」などの事例テンプレートが充実
- 訓練結果はレポートでしっかり分析。どの部署が特に弱いか、どんな傾向があるかが見える化
- 年間スケジュールや社内勉強会キットも一緒に提供されるものが便利
こうしたサービスを活用すれば、教育の手間も軽減され、全社での取り組みもスムーズに進みます。
まとめ
3回にわたってお届けしてきた「フィッシングレポート2025」を中心にしたフィッシング詐欺対策シリーズ。最後にもう一度、大切なポイントをおさらいしましょう。
- 知識を持つだけでは不十分。行動に移すことが重要です。
- IT部門だけでなく、すべての部署が連携して対策を。
- 「教育」だけでなく「訓練」を通して、気づける力を育てましょう。
これからのセキュリティ対策は、「引っかからない力」も含めた“人”がカギです。気づける人が増えることで、会社全体のリスクも減らせます。
できるところから一歩ずつはじめていきましょう!
出典
📄 フィッシング対策協議会『フィッシングレポート2025』
実際の攻撃事例をもとにした訓練を体験し、自社の脆弱性を可視化してみませんか?
「うちでもやってみたいけど、いきなりは不安…」
そんな企業様に向けて、無料デモ体験や資料ダウンロードもご用意していますので、サービスサイトなどぜひご確認ください!
<アクモスのセキュリティサービス紹介>
標的型攻撃メール訓練サービスの概要
<アクモスのセキュリティサービス紹介>
TMT3ヶ月プラン・料金の詳細
<資料で検討したい場合>
サービス資料のダウンロード
<問い合わせしたい場合>
お問い合わせ・導入相談
<2ヶ月間無料で体験できる無料プランで試してみたい場合>
Freeプランのお申込みはこちら